古くなった畳や、リフォーム・引っ越しなどで不要になった畳をどう処分すればよいか悩んでいませんか?
畳は1枚20〜30kgと重く、自治体回収やクリーンセンターへの持ち込み、業者依頼など、処分する方法によって費用・手間・スピードが大きく異なります。
この記事では畳の処分方法をわかりやすく比較し、費用の目安や目的別に最適な選び方を紹介します。
| 処分方法 | 費用目安(1枚) | 特徴 |
| 自治体粗大ごみ回収 | 400〜1,200円 | 最も安いが日程調整が必要 |
| 小さく切って可燃ごみで処分 | 無料〜袋代のみ | 切断の手間と粉じん対策 |
| クリーンセンターに持ち込み | 数百円(重量制) | 当日処分可能、車が必須 |
| ホームセンター・ニトリ | 2,000〜4,400円 | 家具購入時回収が中心 |
| 畳屋の引き取り | 1,650〜2,200円 | 張り替え時は安い場合あり |
| 不用品回収業者に依頼 | 2,000〜5,000円 | 搬出込みで便利、業者選定注意 |
| 譲渡・リサイクル | 無料 | 条件次第で無料処分可能 |
畳の状態や処分したい人の環境によって最適な畳の処分方法が変わってきます。この記事を参考に、自分にピッタリな処分方法を見つけてください。
\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ
畳の処分はどうすればいい?基本ルールと知っておきたい注意点

畳は重くかさばるため、一般ごみと同じ感覚で捨てることはできません。自治体ごとに処分の扱いが異なり、粗大ごみとして予約が必要な場合や、切断すれば可燃ごみで出せる場合もあります。
また、畳には寿命や処分に適したタイミングがあり、費用も方法によって変わります。まずは畳を処分する基本ルールと注意点を押さえておきましょう。
畳は粗大ごみ?可燃ごみ?自治体ルールの違い
畳の処分方法は住んでいる地域の自治体ルールによって異なります。多くの自治体では畳は粗大ごみ扱いになり、1枚ごとに処理券を購入して予約したうえで回収してもらう流れです。
一方で、畳をカットして規定サイズ(45cm角程度)まで小さくすれば可燃ごみとして出せる地域もありますが、畳は重さがあるうえ、内部にわらや断熱材が使われているため切断作業は大変です。
1枚あたりの処分費用相場と重量・サイズ別の扱い
畳1枚の処分費用は、処分方法や畳の種類によって変わります。自治体の粗大ごみ回収では1枚400〜1,200円程度が一般的。
軽量のスタイロ畳(発泡スチロール芯)であれば安く、重い本畳(わら床使用)は高くなる傾向があります。持ち込み可能なクリーンセンターがある地域なら、重量で計算されるため数百円で済むため確認しましょう。
畳は1枚でおよそ5〜7kg、重い本畳では20〜30kg以上になることもあるため、搬出のしやすさも処分方法を選ぶ判断材料です。
カビ・破損・DIYリフォームで不要になった畳を処分するタイミング
畳はおよそ8〜10年が寿命とされ、表面の「畳表」を裏返して再利用しても15年程度が目安。カビやダニが大量発生していたり、表面が破れて下地が見えてしまう場合は処分を検討する時期です。
DIYで和室をフローリングにするリフォーム時には畳を全て撤去することになります。
畳を粗大ゴミとして処分する方法と料金相場

畳を処分する際、もっとも一般的なのが自治体の粗大ごみ回収を利用する方法です。料金は1枚あたり400〜1,200円程度と比較的安価で、回収日も指定できます。
事前申し込みや処理券の購入が必要で、予約枠が埋まると回収が数週間先になるため早めの手続きがおすすめです。
畳を粗大ごみとして捨てる流れ
粗大ごみとして畳を処分する場合は自治体が定めた手順に従いましょう。以下は一般的な流れですが、地域によって細部が異なるため事前確認が必要です。
粗大ごみ受付センターに電話やWebから申し込みます。畳の枚数やサイズ(1枚か半畳か)を伝えると、回収日を決めてくれます。予約は数日〜1週間以上先になることもあるため、余裕をもって手続きしておくと安心です。
回収日が決まったら、コンビニや郵便局で粗大ごみ処理券を購入します。料金は1枚あたり400〜1,200円程度で、地域ごとに差があります。処理券は当日、作業員が見やすい位置に貼り付けてください。
回収日の朝になったら、指定された場所(玄関先や集合住宅のゴミ置き場など)に畳を出します。前日に出すと雨で濡れて重くなったり、風で動いてしまう恐れがあるため、必ず当日の朝に出すようにしましょう。作業員が回収すれば、処分は完了です。
この方法は料金が安く確実に処分できる点が大きなメリット。
畳を粗大ごみ回収に出すときの注意点と搬出時のポイント
畳は1枚で20〜30kgほどになることもあり、搬出時に腰を痛めるケースもあります。集合住宅では廊下やエレベーターのサイズによっては搬出経路の確保が必要です。
雨で濡れると重量が増し扱いがさらに大変になるため、できれば天候の良い日を選ぶか防水シートを用意すると安心です。
\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ
畳を可燃ごみとして処分する方法と切り方・安全対策
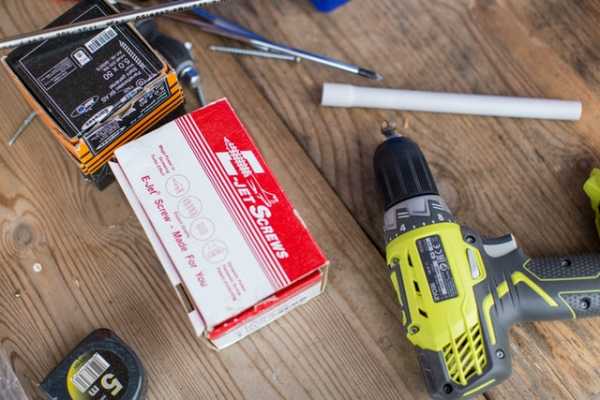
畳を可燃ごみとして処分できる地域では、処理費用が無料または非常に安いのが特徴です。ただし、自治体のルールでサイズ制限やごみ袋の指定があり、畳を切る作業が必要です。
畳を可燃ごみに出せる条件と地域のルールを確認しよう
- 45cm角以内にカットできること
- 指定の可燃ごみ袋に入れ、口をしっかり縛ること
- 1〜2枚程度までの少量処分であること
地域ごとに条件は異なり、袋の材質指定や収集日制限がある場合もあります。可燃ごみとして畳を捨てたい場合は、必ず自治体の公式サイトや分別ガイドで確認してから作業を進めることが重要です。
畳を可燃ごみに出すための切り方と必要な道具
畳を可燃ごみとして処分するには、指定袋に入る大きさ(45cm角程度)に切断する作業が必要です。ここでは、安全に切るための道具と手順を紹介します。
- 大型カッターまたは丸ノコ
- 作業用手袋と保護メガネ
- 養生シート(床や周囲を保護)
切断には大型カッターまたは丸ノコを使用します。カッターを使う場合は刃をこまめに折って切れ味を保ちましょう。ケガ防止のために作業用手袋と保護メガネも必須。
畳は内部にわら床や発泡スチロール芯が使われており、一度に切り落とそうとすると力がかかりすぎて危険です。表面から何度か切り込みを入れて、少しずつ分割すると安全に作業できます。切りくずが舞いやすいので、養生シートを敷くと後片付けが簡単になります。
カットした畳を指定の可燃ごみ袋に入れ、口をしっかり縛ります。袋が破れやすい場合は二重にすると安心です。
畳を可燃ごみに出すときの安全対策と注意点
- 手袋・ゴーグル・マスクを着用する
- 屋外または換気の良い場所で作業する
- 安定した作業台を確保する
畳内部に針金や金属が含まれている場合があり、工具が当たると火花が出ることがあります。
住んでいる地域のクリーンセンターに直接持ち込む方法と処分料金

畳を安く処分したいならクリーンセンターに直接持ち込む方法があります。自分で運搬する手間はありますが、その日のうちに処分できて料金も比較的安いのが特徴です。
畳をクリーンセンターに持ち込む際の搬入条件と受付方法
- 軽トラックやワゴン車などで自分で運ぶことができること
- 事前予約が必要な施設があるため事前確認すること
- 受付時間や休業日を守って搬入すること
畳は1枚あたり20〜30kgと重く、大きさもあるため、軽トラックやワゴン車など積載量に余裕がある車が必要です。普通車では載せられないことが多いので注意しましょう。
クリーンセンターによっては事前予約が必要な場合があります。電話やWebでの予約が一般的です。受付時間や休業日も施設ごとに異なるため、搬入前に公式サイトで確認してください。
搬入当日は身分証や搬入申請書を求められることがあります。また、居住する自治体内の施設でなければ利用できないこともあるため注意してください。条件を満たしていれば、その日のうちに処分を終えられます。
クリーンセンターでは自治体が指定する施設での受付になります。
畳をクリーンセンターに持ち込んだ場合の料金目安とメリット
- 料金は重量制(10kgあたり数十円〜数百円程度)
- 畳1枚で数百円程度の費用になることが多い
- その日のうちに処分が完了する
クリーンセンターに持ち込んで処分する方法の最大のメリットは、予約さえすればすぐに処分できることです。粗大ごみ回収のように回収日を待つ必要がなく、1枚から複数枚までまとめて処理できます。
ホームセンターやニトリで畳を引き取ってもらう方法

自治体の粗大ごみ回収やクリーンセンターへの持ち込み以外に、ホームセンターやニトリで畳を引き取ってもらう方法もあります。家具購入や配送サービスとあわせて利用できることが多く、搬出の手間を減らしたい人向きです。
ニトリで家具購入時に畳を回収してもらう条件と料金
ニトリでは家具購入時に配送サービスを利用すると、不要になった畳を引き取ってもらえる場合があります。
- 家具購入時に配送サービスを利用することが条件
- 新しく購入する家具と同等サイズ・数量まで引き取りが可能
- 料金は1回につき4,400円(畳1枚だけでも同料金)
ニトリの家具引き取りサービスは購入と同時利用が前提で、畳だけの単品回収は基本的に対応していません。
ホームセンターで畳を回収してもらう場合の費用と条件
一部のホームセンターでは畳やカーペットなどの大型廃材を回収するサービスを実施している店舗があります。
- 料金相場は1枚あたり2,000円前後
- 一部店舗では家具・建材とあわせてのみ回収可能
- 受付方法や条件は店舗ごとに異なる
実施店舗は限られており、条件もバラバラです。処分を検討する際は近隣店舗のサービスページや問い合わせ窓口で詳細を確認しておきましょう。
店舗ごとに対応が異なるため事前確認が必要なポイント
ホームセンターやニトリでの畳回収は便利な反面、店舗ごとに対応内容が大きく異なるのが特徴です。
- 回収自体を実施しているか
- 回収できる数量やサイズの上限
- 料金の計算方法(1枚単位か1回単位か)
- 配送・搬出条件(玄関前のみ対応など)
IKEAと無印良品では畳の回収は対象外|家具購入時のみ対応の可能性
IKEAでは新しい家具購入時に有料の家具引き取りサービスを利用できますが、対象はテーブルやベッドなど家具類に限定されることがほとんど。無印良品も同様に家具引き取りを実施していますが、畳のような床材・建材は回収対象外です。
- IKEAの家具回収サービスは新規購入と同時利用が条件
- 畳のような床材や建材は回収対象外となる場合が多い
- 無印良品も家具引き取りを行っているが畳は基本的に対象外
- 店舗や時期によって対応が異なるため必ず事前に確認が必要
店舗判断で引き取り可能な場合もあるため、購入時に店舗スタッフへ相談すると対応してもらえる可能性があります。
畳屋に引き取ってもらう方法とかかる費用

畳屋に依頼して回収してもらう方法もあります。新調や張り替えを依頼するタイミングで回収してもらえば、費用を抑えられるケースが多いのが特徴です。
畳張り替え・新調と同時の回収なら安くなる理由
畳を張り替えたり新調したりする際は、古い畳を同時に回収してもらえる場合があります。この場合、単独で処分を依頼するより費用が安くなるのが特徴です。
- 畳の配送と回収を同時に行える
- 作業スタッフがすでに現場にいるため追加人件費が少ない
- 廃棄処分をまとめて行えるためコストが下がる
交換作業に処分が含まれていると回収費用を個別に負担する必要がなくなり、結果としてコストを抑えられます。
畳1枚あたりの引き取り料金相場
- 相場は1枚あたり1,650円〜2,200円前後
- 地域や畳の種類(本畳・スタイロ畳)で変動
- 搬出条件(階段作業・大型物件)で追加料金になる場合あり
畳屋に処分のみを依頼する場合、作業費と運搬費が別途かかるケースがあります。複数枚の処分ではまとめて依頼すると単価が下がることもあるため、見積もり時に枚数と料金を確認すると安心です。
無料で畳を回収してもらえる条件と問い合わせ時の確認項目
畳屋の中には、条件がそろえば無料で古い畳を回収してくれるところもあります。費用をかけずに処分できる可能性があるため、該当する条件をチェックしておきましょう。
- 張り替えや新調と同時に依頼する
- 数量が少なく、搬出が容易であること
- 地域の回収ルートに含まれている場合
不用品回収業者に依頼した場合の費用と選び方

畳を早く処分したい場合や、自力で搬出できない場合は不用品回収業者に依頼する方法がおすすめです。
即日対応や搬出込みで依頼できるため、手間をかけずに処分したい人に向いていますがし、業者によって料金差や対応品質に幅があるため選び方には注意が必要です。
1枚あたりの料金相場と積み放題利用時のコスト
- 畳1枚あたりの処分費用は2,000円〜5,000円が目安
- 軽トラパック利用時は10,000円前後で複数枚まとめて処分可能
- 階段作業・夜間回収などで追加料金が発生する場合がある
畳だけを単独で回収してもらうと割高になりがちです。軽トラパックのような複数品目をまとめて回収するプランを利用すれば、畳以外の不用品も同時に処分できてコストが下がるケースがあります。
即日対応で搬出込みの畳回収を依頼する場合のメリット
不用品回収業者に依頼すればその日のうちに畳を処分でき、搬出作業まで任せられるのが大きな特徴です。特に引っ越しや急なリフォームで時間が限られている時に便利です。
- その日のうちに処分できる
- 重い畳でも搬出から任せられる
- トラック・人員込みのため負担が少ない
悪質業者に注意!料金トラブルを防ぐチェックポイント
- 見積もり書を発行してもらう
- 追加料金の条件を事前に確認する
- 古物商許可や産廃収集運搬業許可を持っているか確認する
中には法外な追加請求をする悪質業者も存在します。
\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ
無料で畳を処分する方法|譲渡・再利用・リサイクルで費用ゼロにする

畳を無料で処分したい場合は、譲渡・再利用・リサイクルを活用する方法があります。手間はかかりますが、費用をかけずに処分できるだけでなく、再利用で環境にも優しいのが特徴です。
ジモティーやSNSで欲しい人に譲る
- ジモティーやフリマアプリを利用して譲渡先を探す
- SNSで呼びかけて欲しい人に引き取ってもらう
- 農作業やペット用などで需要がある場合がある
畳は農業・ペット飼育・作業場の床材などに再利用する目的で欲しがる人がいます。
農業用・DIY素材として再利用されるケース
- 畑や庭の雑草防止用に利用
- ガレージや作業場の養生マットとして活用
- DIY家具やペット用マットの素材にリメイク
古い畳でも農家やDIY愛好家にとっては価値がある場合があります。
リサイクルショップや畳リメイク利用時のポイント
- 琉球畳や特殊な畳はリサイクルショップで売却できる
- リメイク業者に相談すると素材として再利用できる場合がある
- 事前に写真を送って状態確認をしてもらうのがおすすめ
一般的な畳はリサイクルショップでの引き取りが難しいこともありますが、特殊なサイズや新品に近い状態なら引き取ってもらえることがあります。
畳を処分する費用の比較と目的で選ぶおすすめの処分方法

畳を処分する方法は複数ありますが、費用・手間・スピードが大きく異なります。ここでは、代表的な処分方法を比較表で整理し、目的別におすすめの方法を紹介します。
畳の処分方法別の費用・手間・スピード比較表
| 処分方法 | 費用相場(1枚あたり) | 手間 | スピード |
| 自治体の粗大ごみ回収 | 400〜1,200円 | 申込・搬出あり | 回収日まで待機 |
| クリーンセンターに持ち込み | 数百円(重量制) | 自分で運搬 | 即日処分可能 |
| 切って可燃ごみで処分 | 無料〜数十円(袋代程度) | 切断作業が必要 | 即日または収集日 |
| 畳屋に引き取り依頼 | 1,650〜2,200円 | 依頼・立会いが必要 | 当日または数日以内 |
| ホームセンター・ニトリ | 2,000円〜4,400円 | 条件付き(購入時など) | 即日〜数日 |
| 不用品回収業者 | 2,000〜5,000円(軽トラ1台10,000円前後) | 搬出不要 | 即日可能 |
| 譲渡・リサイクル | 無料 | 探す・交渉が必要 | 引き取り時に完了 |
目的別で選ぶおすすめの畳処分方法|安さ・即日・手間削減で比較
| 目的 | おすすめの処分方法 | ポイント |
| 安さを重視 | 自治体の粗大ごみ回収/クリーンセンター持ち込み/可燃ごみ処分 | 費用が最も安い。特に少量なら切断して可燃ごみが最安 |
| 即日で処分したい | 不用品回収業者/クリーンセンター持ち込み | 即日処分が可能。不用品回収業者は搬出込み対応 |
| 手間をかけたくない | 不用品回収業者/家具購入時のホームセンター・ニトリ回収 | 搬出や運搬を任せられるため労力が少ない |
処分にかける優先度(費用・スピード・手間)によって最適な方法は異なります。自分の状況に合わせて処分方法を選びましょう。
\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ
畳を捨てるタイミングと寿命

畳は定期的なメンテナンスで長く使えますが、寿命を過ぎるとカビやダニの発生・劣化が進行します。また、リフォームやDIYでフローリング化する場合にも処分が必要です。
畳の寿命(8〜10年)と交換サイクル
- 畳表(い草部分)の寿命は4〜5年
- 畳床(芯材部分)の寿命は8〜10年
- 裏返し・表替えで延命可能(最長15年程度)
畳は定期的に裏返し(3〜5年目)や表替え(5〜8年目)をすることで寿命を延ばせます。
カビやダニ被害で早期交換が必要なケース
- カビの発生が広範囲に及んでいる
- ダニ被害が続いている
- アレルギー症状の原因になっている
畳は湿気を吸いやすく、風通しが悪い部屋や布団の敷きっぱなしでカビやダニが発生します。
リフォームやDIYで畳を撤去するタイミング
畳を撤去するタイミングとして多いのは、和室をフローリングに変更するリフォームを行う時。畳を外すことで床材の自由度が高まり、カーペットやフローリング材など好みの内装に変えられます。
- 和室をフローリング化する時
- 床下の断熱リフォームを行う時
- 部屋の用途を大きく変更する時
カビや虫害の防止や部屋の使い勝手を向上させたいといった目的で畳を撤去する人が多いです。
畳を処分するときの注意点|安全・ルール・業者トラブルを防ぐために

畳は重量があり、サイズも大きいため処分時に事故やトラブルが起こりやすいです。ここでは安全面・ルール確認・業者選びの3つの視点から注意点を解説します。
重たい畳を一人で運ばない|ケガや壁・床の破損リスク
- 畳1枚の重さは20〜30kgあり、長さは約180cm
- 無理に一人で運ぶと腰を痛めやすい
- 狭い通路や階段では壁や床を傷つける危険がある
搬出時は必ず二人以上で作業するか、台車やスライダーを用意してください。
畳を切断する時は防護具を必ず着用する|粉じんと刃物事故対策
- 畳内部にはわらや発泡スチロールが詰まっている
- 切断時に粉じんが舞い、カッターや丸ノコでケガをする危険がある
- 切りにくい芯材で刃が折れやすい
切断時は手袋・ゴーグル・マスクを必ず着用しましょう。
自治体ルールを確認してから処分する|収集不可・持ち帰りを防ぐ
- 自治体によって粗大ごみか可燃ごみかの扱いが異なる
- ルールに従わないと回収されず、持ち帰りになることがある
切れば可燃ごみと思い込んで出すと、サイズオーバーで回収不可になることがあります。必ず公式サイトや窓口でルールを確認し、処理券の購入や予約を済ませてから出しましょう。
不用品回収業者の高額請求に注意する|見積書と許可証を必ず確認
- 電話だけの即決や見積書なしは危険
- 作業後に高額請求されるトラブルが多い
- 産業廃棄物収集運搬業許可や古物商許可を持つ業者を選ぶのが基本
依頼時は見積書を必ずもらい、追加料金の条件を確認してください。口コミや許可証の有無も確認して、不明点は事前に質問しておくと安心です。
\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ
いらなくなった畳の処分でよくある失敗例と防ぎ方
畳は重量やサイズの大きさに加え、自治体ルールの違いや作業時のリスクも多い不用品です。ここでは、実際にあった失敗談をもとに防止策を紹介します。
紹介する失敗談は実際に回収現場でお客様から直接聞いた話をまとめたものです。実際の体験や経験をもとにしているので、処分するときの参考にしてください。
自治体の回収ルールを確認せず置き去りにされた
自治体によって畳は粗大ごみ扱いだったり、切断すれば可燃ごみで出せるなどルールが異なります。ルールを確認せずに出してしまい、回収されないケースがあります。
可燃ごみで出せると思い込み、そのまま置いたら翌日には『規格外で回収不可』のシール。再度予約と処理券購入で、予定がすっかり狂いました。
40代|会社員|引っ越し準備で畳を処分
粗大ごみの予約が必要と知らず、出した畳がそのまま残っていました。近所の目も気になり、軽トラで直接搬入することに…。
60代|自営業|和室のリフォームで畳を処分
当日になって回収されず置き去りになると、時間も費用も余計にかかります。精神的にも負担が大きい失敗です。
- 自治体の公式サイトや窓口で回収ルールを確認する
- 処理券や予約の有無を事前に確認する
- 不明点は回収日前に問い合わせる
無理に一人で運んでケガをした
畳は1枚20〜30kgと重く、長さもあり運びにくい不用品です。無理をして一人で持ち出そうとすると、ケガのリスクが高まります。
軽いと思って一人で持ち上げた瞬間、腰に激痛が走りました。その後数日動けず、処分どころではありませんでした。
30代|配送業|実家の片付けで畳を処分
一人で玄関まで運んだ際に手首をひねってしまい、病院に行くことになりました。
50代|主婦|模様替えで畳を撤去
作業中のケガは処分だけでなく生活にも影響します。無理をして後悔するケースは少なくありません。
- 二人以上で協力して作業する
- 台車やスライダーを用意する
- 体力に不安がある場合は業者に依頼する
畳の切断作業でケガや室内汚れが発生
畳を可燃ごみに出すために切断する作業は危険を伴います。刃物でのケガや粉じんによる室内の汚れが発生することがあるので気を付けましょう。
カッターが滑って指を切ってしまい、血が止まらず焦りました。敷いていたカーペットも血で汚れてしまいました。
20代|学生|アパートの退去で畳を処分
室内で切ったら粉じんだらけで掃除が大変に。作業後も細かいゴミが残り、後始末に時間を取られました。
40代|会社員|DIYでフローリングにした際に畳を処分
切断作業は一見簡単に見えますが、ケガや清掃負担のリスクが高いです。
- 屋外または換気の良い場所で作業する
- 手袋・ゴーグル・マスクなど防護具を着用する
- 自信がない場合は専門業者に依頼する
畳の処分では、ルールの誤解や無理な作業、刃物の扱いといった失敗が目立ちます。どのケースも事前の確認と準備で防ぐことができるので参考にしましょう。
\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ
畳の処分方法に関するよくある質問
畳は燃えるごみで出せますか?
一部の自治体では、畳を切断して指定のごみ袋に入れれば可燃ごみで処分できます。ただし、サイズ制限や枚数制限があるため、必ず地域の分別ルールを確認してください。
畳1枚の処分費用はどれくらいかかりますか?
自治体の粗大ごみ回収なら1枚400〜1,200円程度、クリーンセンターへの持ち込みなら数百円で済むことが多いです。不用品回収業者の場合は搬出込みで1枚2,000〜5,000円程度が目安です。
畳を無料で処分する方法はありますか?
張り替えや新調と同時に畳屋に依頼したり、ジモティーやSNSで譲渡相手を探せば無料で処分できることがあります。ただし条件付きのため、事前に対応可否を確認しましょう。
畳は何年くらいで交換するのが目安ですか?
畳表は4〜5年、畳床は10〜20年程度が交換の目安です。カビやダニが発生した場合や沈み込みが目立つ場合は早めの交換がおすすめです。
畳の処分に予約は必要ですか?
自治体の粗大ごみ回収は事前予約が必要な場合がほとんどです。不用品回収業者は即日対応も可能ですが、繁忙期は予約が取りにくくなるため早めに問い合わせましょう。
まとめ|目的に合わせて安全かつ効率的に畳を処分しよう
畳は大きくて重いため、処分には計画と正しい方法選びが欠かせません。
今回紹介した方法を整理すると、安く処分するなら自治体回収やクリーンセンター、手間をかけずに済ませたいなら不用品回収業者、無料で済ませたいなら譲渡やリサイクルが向いています。
一度に複数枚を処分する場合や急ぎの撤去が必要な場合は、費用とスピードのバランスを見極めて選ぶことが重要です。
無理な一人作業や切断時の事故、悪質業者の高額請求といったリスクもあります。安全のためには二人以上での運搬や防護具の着用、そして業者依頼時の見積書・許可証確認を忘れないようにしましょう。
畳の処分は面倒に感じますが、計画的に進めれば短時間で終わり、住まいがすっきりと整います。自分に合った方法を早めに選び、安全でスムーズに処分しましょう。
このサイトでは不用品回収歴8年のプロが、信頼できる不用品回収業者の選び方や捨て方がわからない物のお得な処分方法について紹介しています。
相見積もり先や安心して利用できる不用品回収業者を探していたら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

\ 信頼できる業者探しは相見積もりが必須! /
料金・信頼性・対応スピードを比べて決めたい方へ

